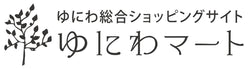ゆにわのお線香 樹木の香り
通常価格
¥2,300
通常価格
セール価格
¥2,300
単価
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした

という梅薫堂(ばいくんどう)の理念に深く共鳴し、
ゆにわでは梅薫堂のお線香を10年以上、愛用しています。
そのご縁から、ゆにわと梅薫堂が共同開発したお線香です。
3種類の個性的な香り
「ゆにわのお線香」には現在、3種類の香りがあります。香りは好みで使っていただいても構いませんし、特に「樹木の香り」は空間を消臭したいときに、「まこも」はスッキリ浄化したいときに、「蓮」は純粋に香りを楽しみたいときやお客さまをお迎えするときにおすすめです。

ゆにわのお線香 蓮(はす) |

ゆにわのお線香 まこも |
樹木の香り 【このページの商品】

「お線香をつくるなら、どんな香りにするか?」
と考えていたところ、かねてからご縁のあった古代ヒノキ職人の方が、偶然、「何かに使ってもらえないか?」と、わざわざゆにわに持ってきてくださったのです。
こちらのお線香を焚くと、 たった一本で空間が清らかになり、心の奥にあたたかみが灯ります。
まこもの香り

「 備長炭麗 ゆにわのお線香 樹木の香り」に続き、ゆにわと梅薫堂が共同開発したのが、こちら「マコモ」のお線香です。
マコモは、日本各地に自生しているイネ科の植物。
心に蓄積したノイズを澄み切らせ、自然と呼吸が深くなるような、落ち着く香りです。
お掃除のとき、空間を浄化したいときには特におすすめです。
まこもの香りはこちら
蓮の香り

その凛とした姿は、混沌の時代の中でも、純粋な心で生きる勇気を、わたしたちに与えてくれます。
闇があるからこそ、光が見える。そんな光と影のコントラストを、香りで表現したのが本品です。
花の香りを光に、白檀と沈香を影に見立てて、調香しました。
甘く上品で、かつ華やかな、東洋を思わせる香りとなっています。
蓮の香りはこちら
こんな時にお線香でリフレッシュ

香炉もあります

お線香を最後まで余さずに焚ける、寝かせるタイプの香炉(こうろ)です。
安全でお手入れ楽々、ストレスフリー。
ひのき材にレーザーカットで模様をあしらい、インテリアとしても最適な逸品です。

木香炉 卍 |

木香炉 麻の葉 |

木香炉 三の字 |
火をつける時のポイント

線香は火をつける瞬間の「意識(気持ち)」が大切です。
「何も考えずに火をつけるのと、空間がスッキリするのをイメージしながら火をつけるのとでは、全然違います!」という声をいただきます。
火をつける瞬間は、線香と火が出会う瞬間。ぜひ、火をつける瞬間だけでも、気持ちを整えてつけてみてください。
火はライターやマッチでつけていただいて構いませんが、何で火をつけるかでも、雰囲気が変わります。
ゆにわマートでも販売している「美爐空(みろく)キャンドル」や「お米のろうそく」で火をつけていただくことで、よりお線香の浄化力を感じていただけると思います。

美爐空 いとなみ |

「お米のろうそく」20本入 |
開発秘話
以前、このページのお線香を作っている『梅薫堂(ばいくんどう)』さんを、ゆにわマートのスタッフで訪問させていただきました。その時の様子を、スタッフの佐藤想一郎がお届けします。

みなさまは「線香」と聞くと、どのようなイメージがありますか?
仏事で使うイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、癒しや開運アイテムとしても使うことができます。
また、良い香りは、昔から邪気払いとしても使われてきました。たとえば地鎮祭では、悪い気が入らないように四隅で線香を焚きます。空間が良い香りで満たされていたら、それが悪い気から守る「バリア(結界)」になるのですね。
梅薫堂のお線香は自然な香りで、消臭・浄化力も高いものが多く、ゆにわマートではかなり初期の頃から販売していました。たとえば、消臭効果が高い、梅薫堂の「備長淡麗シリーズ」は、ゆにわの各店舗でも使っています(この写真は森の香りですが、他にも白檀や、ラベンダー、梅の香りなどがあります)

訪問するきっかけになったのは、梅薫堂の専務取締役である吉井さんが『ゆにわマート』にご挨拶にいらしてくださったことから。
最初は軽くご挨拶・・・という流れだったのですが、お線香について2時間も、ぶっ通しで語ってくださり、どんな角度から質問をしても、情熱的に答えてくださったのです。
お線香の材料や工程、1つ1つに意味があり、全ての商品に個性がある。吉井さんから商品に対する深い愛が伝わってきました。
そこで今度は、ゆにわマートスタッフが梅薫堂さんにお邪魔させていただくことになり、私も撮影スタッフとして同行しました。

梅薫堂は、嘉永三年(1850年)に創業。淡路島を拠点として線香を販売している老舗企業です。
梅薫堂のお線香の調香は、代々、社長さんがするそうなのですが、吉井社長が高校生のときに、先代の社長が亡くなられてしまったそうです。吉井社長は、先代社長の線香作りは手伝っていましたが、調香のレシピなど、詳しいことは教わっていません。
「まだレシピを聞いてないのに・・・」と悩んでいたある日、なんと夢の中に調香レシピが出てきたのです!梅薫堂のお線香はそういったインスピレーションを受けたり、偶然のご縁でつながったりして開発が始まることがあるそうで、そこから、緻密な研究・開発を積み重ねて作られています。
たとえば、一般的なお線香は材料に化学香料が使われていますが梅薫堂さんのお線香は天然素材にこだわってつくられています。
「お客様のためを思えば、天然素材を使うのは当たり前」・・・と、商品が届く先のお客様のことを一心に考えながら作られている姿勢が言葉からも強く伝わってきます。
▼調香に使う、天然の材料

実は、梅薫堂の線香は、そう簡単に真似できない特別な技術も使われており、一部、高級な素材も使われています。・・・にもかかわらず「良いものを、多くの人に使っていただきたい」と考え、手に取りやすい価格にしているのだそうです。
「もっと目立つように、アピールしたらいいのに!!」と思ってしまうのですが、社長は「本当にいいモノはお客様が分かっている」「最後は、うちの線香にたどり着く人は多い」と言います。
工場は何箇所かあり、手作業で線香を作る工場も残っています。吉井崇行さん(息子さん)の案内で工場に入ると80代以上の梅薫堂の社員の方々が、黙々と線香を作っています。
挨拶をすると、笑顔で挨拶を返してくださったのですが、その後は真剣な眼差しで、ひたすら仕事をされています。言葉数は少なくとも、まるでお線香を使う人の幸せを祈るかのような雰囲気が、その背中や所作から、ひしひしと伝わってきました。
ファインダー越しにその美しい動きを見ているだけで心が静まるようです。そして何より印象的だったのが、専務取締役である吉井さんが、職人さんたちよりも腰が低く、「ありがとうございます」「失礼します」といった声をかけ、気にかけていたことです。
それがあまりに自然だったので、普段から職人さんたちを尊重されていることが伝わってきました。
▼〝はかり〟を使わずに、竹串1本で一箱分に分けています。職人の技です。

▼線香を束ねるための紙も、1つ1つ手作業で巻いていきます。

この「巻く」工程は、最初は、素麺に紙を巻く機械でできないか試したそうですが、機械を使うと線香が何本か折れてしまいました。
吉井さんは言います。
「素麺だと何本か折れていても気にならないのに、線香だと数本折れているだけでクレームがきてしまう。
それに、強く巻きすぎると線香が取り出しにくくなり、逆に弱すぎると線香がバラバラになってしまうんです。その微妙な力加減は、やっぱり人の手でしかできないんですよね。」
とは言っても、全ての商品や工程を手作業にしたら、生産量が減ってしまったり、かたちにバラつきが出てしまったりします。
かたちのバラツキは「味がある」と思う人もいれば、中には「品質が悪い」と思ってしまう人もいます。また、線香の種類によっては、硬さの関係で、機械を使わないとそもそも作れないものもあるそうです。
そこで、工程が機械化された工場もあります。こちらの工場では、先ほどの手作業の工程がそのまま機械化されていました。
少し見えにくいのですが、下の写真の右奥から線香が素麺のように出てきて板に乗り、今度はその板を手前に写っているように、自動的に重ねていきます。

もちろん全て機械の力で終わらせるのではなく、一度は必ず、自然の風に当て、人の目で見ます。
▼積み上がっているのが、線香です。

線香は乾き具合が非常に重要だそうで、その乾燥具合は、職人さんが休みの日かどうかに関係なく、自主的に見にきて「目視」で繰り返し確認していると言います。「心配で仕方がない」そんな、まるで我が子を見守るかのような気持ちなのかもなぁ、と想像していました。
*
工場から梅薫堂の会社への帰り道。距離があったため、吉井さんは私たちを車に乗せてくださいました。
車の窓は開いていて、外からは線香の良い香りが漂ってきます。街全体が香りで守られているのか、不思議な安心感がありました。
梅薫堂さんのある地区には、ほかにもたくさんお線香メーカーさんが集まっていると言います。観光庁の「かおり100選」にも認定されているとか。
淡路島の香り文化をたどってみれば、なんと奈良時代にまでさかのぼるそうです。吉井さんは、「日本書紀にはすでに淡路島と香りの関係が記されているんですよ」とおっしゃいます。
「奈良時代、推古天皇のころ、ひと囲いほどの香木が淡路島に漂着しました。当時の島民は、香木というものを知らず、薪と共にかまどで焼きました。すると、その煙は遠くまで類い希なる良い薫りを漂わせたのです。これは不思議な木だと思い、朝廷に献上。これが淡路島と香木との最初の出会いなのです」
淡路島の枯木神社では、香木伝来伝承地として、人の体の大きさくらいある香木(枯木)をご神体として祀っているというのです。
まさに、1300年以上も昔から淡路島は「香りの島」になるべくして、神様からお役目をいただき、導かれてきたのです。
淡路島の枯木神社淡路島って、まさに「香りの島」なんですね。

そんな話を聞きながら、ぽつりと「街全体が、線香の香りがするんですね」と言うと、吉井さんは笑いながら「ここにきた人はみんなそう言うのですが・・・ 僕らはもう線香の香りに慣れすぎちゃったのか、 香らないんですよね」とおっしゃいました。
ご本人にとっては当たり前のことでなんてことはないのかもしれませんが、自然とこういう言葉が出るくらい線香を作る仕事が、生きることと一体になっているのだな、と感じました。
*
家に帰ると、ずっと使っている、梅薫堂の線香が目に入りました。同じ「線香」でも、梅薫堂に行く前と後では、全く違うもののように感じました。
「どれだけの人が、どれだけの思いをこめてどれだけ時間をかけて作ってきたのか・・・」
その背景を感じることで、胸が暖かくなりました。
周りを見渡してみると、他にもたゆにわマートの商品たちが。
「1つ1つに作り手の思いや壮大なストーリーがある」
それは頭では”知って”いたことではありましたが、梅薫堂さんにお邪魔したのをきっかけに、より臨場感を持って感じられるようになったのでした。
仏事で使うイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、癒しや開運アイテムとしても使うことができます。
また、良い香りは、昔から邪気払いとしても使われてきました。たとえば地鎮祭では、悪い気が入らないように四隅で線香を焚きます。空間が良い香りで満たされていたら、それが悪い気から守る「バリア(結界)」になるのですね。
梅薫堂のお線香は自然な香りで、消臭・浄化力も高いものが多く、ゆにわマートではかなり初期の頃から販売していました。たとえば、消臭効果が高い、梅薫堂の「備長淡麗シリーズ」は、ゆにわの各店舗でも使っています(この写真は森の香りですが、他にも白檀や、ラベンダー、梅の香りなどがあります)

訪問するきっかけになったのは、梅薫堂の専務取締役である吉井さんが『ゆにわマート』にご挨拶にいらしてくださったことから。
最初は軽くご挨拶・・・という流れだったのですが、お線香について2時間も、ぶっ通しで語ってくださり、どんな角度から質問をしても、情熱的に答えてくださったのです。
お線香の材料や工程、1つ1つに意味があり、全ての商品に個性がある。吉井さんから商品に対する深い愛が伝わってきました。
そこで今度は、ゆにわマートスタッフが梅薫堂さんにお邪魔させていただくことになり、私も撮影スタッフとして同行しました。

梅薫堂は、嘉永三年(1850年)に創業。淡路島を拠点として線香を販売している老舗企業です。
梅薫堂のお線香の調香は、代々、社長さんがするそうなのですが、吉井社長が高校生のときに、先代の社長が亡くなられてしまったそうです。吉井社長は、先代社長の線香作りは手伝っていましたが、調香のレシピなど、詳しいことは教わっていません。
「まだレシピを聞いてないのに・・・」と悩んでいたある日、なんと夢の中に調香レシピが出てきたのです!梅薫堂のお線香はそういったインスピレーションを受けたり、偶然のご縁でつながったりして開発が始まることがあるそうで、そこから、緻密な研究・開発を積み重ねて作られています。
たとえば、一般的なお線香は材料に化学香料が使われていますが梅薫堂さんのお線香は天然素材にこだわってつくられています。
「お客様のためを思えば、天然素材を使うのは当たり前」・・・と、商品が届く先のお客様のことを一心に考えながら作られている姿勢が言葉からも強く伝わってきます。

実は、梅薫堂の線香は、そう簡単に真似できない特別な技術も使われており、一部、高級な素材も使われています。・・・にもかかわらず「良いものを、多くの人に使っていただきたい」と考え、手に取りやすい価格にしているのだそうです。
「もっと目立つように、アピールしたらいいのに!!」と思ってしまうのですが、社長は「本当にいいモノはお客様が分かっている」「最後は、うちの線香にたどり着く人は多い」と言います。
工場は何箇所かあり、手作業で線香を作る工場も残っています。吉井崇行さん(息子さん)の案内で工場に入ると80代以上の梅薫堂の社員の方々が、黙々と線香を作っています。
挨拶をすると、笑顔で挨拶を返してくださったのですが、その後は真剣な眼差しで、ひたすら仕事をされています。言葉数は少なくとも、まるでお線香を使う人の幸せを祈るかのような雰囲気が、その背中や所作から、ひしひしと伝わってきました。
ファインダー越しにその美しい動きを見ているだけで心が静まるようです。そして何より印象的だったのが、専務取締役である吉井さんが、職人さんたちよりも腰が低く、「ありがとうございます」「失礼します」といった声をかけ、気にかけていたことです。
それがあまりに自然だったので、普段から職人さんたちを尊重されていることが伝わってきました。


この「巻く」工程は、最初は、素麺に紙を巻く機械でできないか試したそうですが、機械を使うと線香が何本か折れてしまいました。
吉井さんは言います。
「素麺だと何本か折れていても気にならないのに、線香だと数本折れているだけでクレームがきてしまう。
それに、強く巻きすぎると線香が取り出しにくくなり、逆に弱すぎると線香がバラバラになってしまうんです。その微妙な力加減は、やっぱり人の手でしかできないんですよね。」
とは言っても、全ての商品や工程を手作業にしたら、生産量が減ってしまったり、かたちにバラつきが出てしまったりします。
かたちのバラツキは「味がある」と思う人もいれば、中には「品質が悪い」と思ってしまう人もいます。また、線香の種類によっては、硬さの関係で、機械を使わないとそもそも作れないものもあるそうです。
そこで、工程が機械化された工場もあります。こちらの工場では、先ほどの手作業の工程がそのまま機械化されていました。
少し見えにくいのですが、下の写真の右奥から線香が素麺のように出てきて板に乗り、今度はその板を手前に写っているように、自動的に重ねていきます。

もちろん全て機械の力で終わらせるのではなく、一度は必ず、自然の風に当て、人の目で見ます。

線香は乾き具合が非常に重要だそうで、その乾燥具合は、職人さんが休みの日かどうかに関係なく、自主的に見にきて「目視」で繰り返し確認していると言います。「心配で仕方がない」そんな、まるで我が子を見守るかのような気持ちなのかもなぁ、と想像していました。
*
工場から梅薫堂の会社への帰り道。距離があったため、吉井さんは私たちを車に乗せてくださいました。
車の窓は開いていて、外からは線香の良い香りが漂ってきます。街全体が香りで守られているのか、不思議な安心感がありました。
梅薫堂さんのある地区には、ほかにもたくさんお線香メーカーさんが集まっていると言います。観光庁の「かおり100選」にも認定されているとか。
淡路島の香り文化をたどってみれば、なんと奈良時代にまでさかのぼるそうです。吉井さんは、「日本書紀にはすでに淡路島と香りの関係が記されているんですよ」とおっしゃいます。
「奈良時代、推古天皇のころ、ひと囲いほどの香木が淡路島に漂着しました。当時の島民は、香木というものを知らず、薪と共にかまどで焼きました。すると、その煙は遠くまで類い希なる良い薫りを漂わせたのです。これは不思議な木だと思い、朝廷に献上。これが淡路島と香木との最初の出会いなのです」
淡路島の枯木神社では、香木伝来伝承地として、人の体の大きさくらいある香木(枯木)をご神体として祀っているというのです。
まさに、1300年以上も昔から淡路島は「香りの島」になるべくして、神様からお役目をいただき、導かれてきたのです。
淡路島の枯木神社淡路島って、まさに「香りの島」なんですね。

そんな話を聞きながら、ぽつりと「街全体が、線香の香りがするんですね」と言うと、吉井さんは笑いながら「ここにきた人はみんなそう言うのですが・・・ 僕らはもう線香の香りに慣れすぎちゃったのか、 香らないんですよね」とおっしゃいました。
ご本人にとっては当たり前のことでなんてことはないのかもしれませんが、自然とこういう言葉が出るくらい線香を作る仕事が、生きることと一体になっているのだな、と感じました。
*
家に帰ると、ずっと使っている、梅薫堂の線香が目に入りました。同じ「線香」でも、梅薫堂に行く前と後では、全く違うもののように感じました。
「どれだけの人が、どれだけの思いをこめてどれだけ時間をかけて作ってきたのか・・・」
その背景を感じることで、胸が暖かくなりました。
周りを見渡してみると、他にもたゆにわマートの商品たちが。
「1つ1つに作り手の思いや壮大なストーリーがある」
それは頭では”知って”いたことではありましたが、梅薫堂さんにお邪魔したのをきっかけに、より臨場感を持って感じられるようになったのでした。
 むすび大学で紹介中
むすび大学で紹介中日本が誇る“結び”の精神によって古今東西の学問を和合させて、新しい文化の創造を目指す「むすび大学チャンネル」でも紹介しています。
愛用者の声
 ゆにわマートスタッフ
ゆにわマートスタッフつむこ
樹木の香りで森林浴気分に浸れます。
お気に入りの香り:樹木
ヒノキの清々しい香りが気に入っています。好みもあると思いますが、樹木系の香りは落ち着きがあり、それでいてリフレッシュもできるんですよね。
朝、起きた直後に焚くと、眠っていた空間に爽やかな風が吹いたような、自然の中をお散歩しているような気分になります。

夏など、室内が少し蒸し暑く感じるときにもよく焚いています。ヒノキの香りに包まれていると、なぜか、空気まで涼しくなったように感じるんです。涼しげな香りは、体感温度を下げる効果がある!と個人的に思っています。
香炉はキッチンやリビング、玄関など、コーナーごとに置いてあります。そして、「樹木の香り」を一斉に焚くんです。すると、家中が森!!って感じになります(笑)。
香炉は、ゆにわマートの木香炉をはじめ、使わなくなった器に香炉灰を入れたりして、香炉の代わりに使っています。

ゆにわのお線香は、どれも天然の植物の香りだから、身体にスーッと馴染んでくれて心地よいです。リフレッシュしたい時や、仕切り直したい時にもおすすめ。焚くだけで、ぱっと切り替えられると思います。ぜひ使ってみてください!
朝、起きた直後に焚くと、眠っていた空間に爽やかな風が吹いたような、自然の中をお散歩しているような気分になります。

夏など、室内が少し蒸し暑く感じるときにもよく焚いています。ヒノキの香りに包まれていると、なぜか、空気まで涼しくなったように感じるんです。涼しげな香りは、体感温度を下げる効果がある!と個人的に思っています。
香炉はキッチンやリビング、玄関など、コーナーごとに置いてあります。そして、「樹木の香り」を一斉に焚くんです。すると、家中が森!!って感じになります(笑)。
香炉は、ゆにわマートの木香炉をはじめ、使わなくなった器に香炉灰を入れたりして、香炉の代わりに使っています。

ゆにわのお線香は、どれも天然の植物の香りだから、身体にスーッと馴染んでくれて心地よいです。リフレッシュしたい時や、仕切り直したい時にもおすすめ。焚くだけで、ぱっと切り替えられると思います。ぜひ使ってみてください!
 木竜一翔さん
木竜一翔さんリフレッシュしたいときに
お気に入りの香り:樹木
僕は勉強で疲れた時など、リフレッシュしたい時に使うことが多いです。木の香りがするので、自分の部屋にいるのに自然に囲まれているような気分になります。とてもリラックスできるのでとてもおすすめです。


 梅部 部長 セイラ
梅部 部長 セイラとてもいい香り!
お気に入りの香り:蓮
もともと、ゆにわマートのオリジナル線香シリーズが好きで、新たに、蓮の香りが出る、というタイミングに買ってから、ずっと使い続けています。ゆにわマートで扱っている線香のなかで、一番好きな香りです。日常から使っています。特に、今から頑張るぞ!!という時、気持ちを切り替える時などにも使っています。仕事場でも、家でも、毎日使っています。蓮だけにハッスル!って感じなんですよね(笑)。大好きです!
 撮影スタッフ
撮影スタッフえーき
一番好きなお線香です!
お気に入りの香り:まこも
僕はいろんなお線香を使っていますが、その中でもダントツで、このお線香を使っています。ニオイをリセットしたい時、空間が疲れてるなと感じる時などにたいています。「まこも」という日本で大切にされてきた霊草を粉にしたものを線香に練り込んでいるので、禊祓(みそぎはらえ)されるような気持ちにさせてくれます😊ちなみに、僕はこの商品が出た時からずっと使い続けており、切らしたことはありません!オススメの使い方は、一旦部屋の窓を閉めて、まこも線香をつけて、充満したなとおもったら、けむりとともに邪気を吹き送るようなイメージで窓をあけています!空間がスッキリします。


 スタッフ
スタッフあき
いろんなお線香を使い分け✨
お気に入りの香り:蓮
毎日のように、おうちや職場でお線香を焚いているのですが、特にこのゆにわの蓮のお線香はお気に入りです。 備長炭麗シリーズに比べて、ゆにわのお線香シリーズは、お線香自体が細めですが、その分、たくさん数が入ってるので、毎日使ってもけっこうもちます。 そして、蓮のお線香の一番のお気に入りの点は、とても香りがいいところです。 中国線香や、備長炭麗シリーズ、市販のお気に入りのお線香など、 いろいろ揃えて、 その日の気分や、シーンによって使い分けています。仕事場でも、使っています。


 久山将平さん
久山将平さん空間にアクセントを!
お気に入りの香り:蓮、まこも
蓮のお線香は、まこも線香や森のかおり線香を焚いた後に 空間にアクセントをつけるエネルギーアップに使ってます! 良い香りで心がホッとするような 癒される香りで一番使用頻度が多い 最高の線香です。 まこものお線香は、空間の浄化に大助かりです。 日常の掃除の時や帰宅直後に 空間をリセットしたい時に 使っています。 また、初めての一人暮らしの 新居に大量のまこも線香を焚きながら 空間を浄化するのにも使いました。 とても空間がスッキリした感じで 日々の暮らしに欠かせないものとなっています!! ありがとうございます😭

 スタッフ
スタッフあんちゃ
天然のまこもの浄化力✨
お気に入りの香り:まこも
お部屋掃除のときや、空間がどよーんとしているときに、一気に2〜3本焚いてから、窓を開けて換気すると、めちゃくちゃスッキリします!天然のまこもの浄化力に感動!

こちらもおすすめです

ゆにわマートでは、中国に古来から伝わる教え「道教」の修行をしている道士がつくっている〝中国線香〟シリーズも扱っています。
おすすめの使い方は、『ゆにわのお線香 樹木の香り』を使った後に、少しだけ〝中国線香〟を焚く方法です。
〝中国線香〟は、とてもエネルギーが高いため、空間を整える最後の仕上げにも適しています。
(ゆにわのお線香の「蓮」の香りや「まこも」の香りは、それ自体の香りが強く、香りが混ざってしまうため、この使い方をする場合は、香りや煙が弱い「樹木」の香りとの組み合わせをおすすめしています。)
〝中国線香〟が気になる方は、この下のリンクから見てみてくださいね。
中国線香シリーズはこちらから
| 内容量 | 約100g |
| 線香の長さ | 約13.5cm |
| 燃焼時間 | 約30分 |