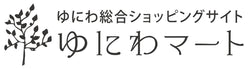[ゆにわオリジナル]ひかりの土鍋
受取状況を読み込めませんでした
ゆにわオリジナル「ひかりの土鍋」
生命の躍動を表現する音楽を響かせた水(サウンドウォーター)を使った愛知県・瀬戸で作られた織部焼の土鍋です。従来の土鍋よりも、さらに光を集めます!
調理時に、遠赤外線を発するので美味しいごはんが炊けます。
普段のお米をもっともっと美味しく炊きたい方におすすめです。
サイズ:4合で美味しく炊き上がります。(推奨)
※5.5合入るサイズですが、
(ごはんを炊く以外にも、煮物料理などにもお使いいただけます)
「土鍋ごはん」はふっくら、つやつや、香ばしい

「もっとおいしいごはんをたべてみたい…」
「電気炊飯器で炊くごはんは味気ないなあ…」
そんな方は、土鍋でごはんを炊いてみてください。
炊き上がって蓋を開けた瞬間、立ち上る湯気、キラキラ光るごはん、
そして、同じお米とは思えないほどの美味しさにびっくりしますよ!

「土鍋ごはん」のおいしさのヒミツ
土鍋は電気炊飯器と違ってゆっくり時間をかけて加熱をすることで、より多くのうまみ成分がお米から出てきます。
土鍋全体がむらなく加熱されることで、水の対流がお米にまんべんなく加えられ、土鍋の蓋の圧によって1粒1粒のお米にうまみがたっぷり。
さらに、土鍋は火を止めた後も熱を保っているので、保温効果の蒸らしが相乗効果をもたらすので、電気炊飯器と炊いたお米とは比べ物にならないほどのうまみがでてきます。
おこげができるのも、ご飯鍋での炊飯の楽しみのひとつですよね♪
ゆにわは「ひかりの土鍋」を使っています
ひかりの土鍋はゆにわのランチやディナーで使わせていただいています。


また、「綾部ゆにわ」でお出ししているごはんは、「ひかりの土鍋」のサイズが大きいもので炊いたご飯を提供しております。


ひと手間加えることでさらにおいしく
「ひかりの土鍋」で炊くときに、お米のなかに
『おいちこ米』 を一つまみ、加えてください。
さらにエネルギーアップしたおいしいごはんが出来上がります。
| 商品名 | ひかりの土鍋(瀬戸焼) |
|---|---|
| サイズ | 直径約27cm(取手含む)、高さ約23cm(蓋を含む)、4合炊き |
| 性能 | IH不可 |
大事なポイント&お手入れ
お使いいただく前に
●土鍋の特性
土鍋には無数の小さな気孔があります。そのため直接火が当たるところばかりでなく、 土鍋全体がゆっくりとあたたまり、食材本来のうまみを引き出してくれます。
●お料理の向き・不向き
ご飯を炊くほかは、おでんやおかゆなどの長く煮込む料理に適しています。火のあたりが柔らかく、火を止めた後でも高温が保たれるので余熱で、よりじっくりと具材の芯まで味が染み込みます。
天ぷら/フライなどの「揚げ物料理」には使用しないでください。
揚げ油が土鍋にしみこんで悪臭の原因になるほか、調理中、鍋にしみこんだ油に引火することもあります。火災の原因になる恐れがあります。
●ひびや気孔について
土鍋の底部分は無数の細かな穴が空いています。熱を加えることで膨張し、冷えると収縮します。その際、小さなひびが土鍋の変化を調節してくれます。ひびは土鍋にとって必要なものです。使うほどひびが入り、煮えやすくて使いやすい土鍋に育っていきます。
●最初に必ず「目止め」を行ってください
土鍋に小さなひびや穴があるため、 そのまま使用すると水が染み出してしまい、ヒビ割れの原因に繋がります。そのため、初めて土鍋をお使いになる時は、その前に必ずおかゆを炊いてください。これを「目止め」といいます。
お米のでんぷんによって、素地の目や穴をふさぎます。
また、水漏れをおさえ、煮立ちがよくなります。
お使いいただく中での注意点
●火にかけるときは弱めの中火から
土鍋は急激な温度変化に弱いため、土鍋が冷えた状態で急に強火をあてると、温度差が大きすぎて割れる原因になります。土鍋を火にかけるときは弱めの中火から、じっくり時間をかけて鍋全体を温めましょう。
●外側は乾いた状態で火にかける
土鍋の底(外側)が濡れてる状態で強火にかけないようにしてください。布巾などで水気を拭きとって、乾燥させて使用してください。
●持つときは火傷に注意
熱い状態の土鍋を扱うときには、取っ手や蓋が熱くなっています。鍋つかみを使い、火傷しないようにご注意ください。テーブルに置くときは必ず鍋敷を敷いてください。新聞紙やぬれ布巾の上に置くと、焦げや割れの原因になりますのでご注意ください。
●金属の調理器具は使わない
調理器具は、なるべく金属製より木製のものを使うことをおすすめします。土鍋の素地や釉薬部分に傷がつかないようにするためです。
土鍋を洗うときの注意点
●汚れた状態の水を入れて放置しない
土鍋は水分がしみこみやすいため、食材を長時間入れたままにしておくと、においがついたりカビが生える原因になります。早めに空にしましょう。
●粗熱がとれてから洗う
炊き終わったら、土鍋の粗熱が取れるまで洗わずに、60~70度程度のお湯を入れてしばらくおいておきます。(急激な温度変化を防ぎ、割れないようにするため)
ある程度冷めて、張り付いているデンプンを浮いてきたら、撫でるように洗ってください。軽く水拭きして、裏返しで乾燥させてください。
●重曹やクエン酸などで洗わないでください
洗浄目的で使うと目詰まりとなり土鍋に染み込むためご利用はお控えください。
●金属製タワシや研磨剤では洗わないでください
金属タワシやメラミンスポンジ、研磨剤入りのクレンザーなどで洗うと、表面が削られて傷がつくので使用をお控えください。
●しっかり乾燥させましょう
土鍋を裏返した状態で乾燥させてください。乾いたように見えても、湿気が残っていることがあります。よりしっかり乾かすことで長持ちし、カビの発生を抑えられます。天日干しもお勧めです。
土鍋にまつわるQ&A
- 土鍋にひびが入ってしまったら?
- ひびは土鍋が育ってきた証拠なので問題ありません。土鍋にはもともと無数の小さな穴やひびがあります。熱を加えることで膨張し、冷えると収縮します。その際、ひびが土鍋の変化を調節してくれます。
ただし、割れる原因になるようなひびもあります。土鍋の淵まで大きくひびが入ってしまった場合は、火にかけると割れてしまう恐れがあるので、使用をお控えください。
- ひびから水漏れしだしたときは?
- 「目止め」を行ってください。おかゆや雑炊、うどんなど、でんぷんを含んだ料理をすることで水漏れが収まります。下記の「目止めのやり方」を参照)初めて使用する前に1回、そして年に2,3回、行うことで安定します。
水漏れが見られたら、その都度おこなってください。
- こげはどうやってとればいい?
- 「しばらく、水やぬるま湯につけてふやかしてから、固めのスポンジでやさしくこすってください。また、重曹を水に溶かして、軽く煮たてることで、焦げつきが柔らかくなり、とれやすくなります。
- 料理のにおいを取る方法は?
- 土鍋に8分目まで水を入れ、茶がら(緑茶やほうじ茶)をひとつかみ入れて10分くらい煮立てます。お茶に含まれる成分がにおいを吸着してくれます。
お茶の代わりに、レモンなどの柑橘類の汁を少し入れて煮立てる方法もあります。
かび臭さを取りたいときは、たっぷりの水にお酢大さじ2,3杯いれて煮たててください。
- かびが生えてしまったら?
- 水洗いでかびを落とし、水気をしっかり拭き取ります。水をたっぷりいれてお酢大さじ2,3杯いれて10分ほど煮ると、かび臭さがとれます。その後、軽く洗ってよく乾かしてください。
土鍋は吸水性が高いため、洗い桶などに入れっぱなしにしていると、においがうつったり、カビが生える原因になります。長期間保管するときは、新聞紙で包んでおくとかびが生えにくくなるのでおすすめです。
- 割れた時は修理してもらえますか?
- 割れたり壊れた場合の修理の対応はしておりません。焼き物の修理は、茶碗などであれば、金継ぎの方法がありえますが、土鍋は高温調理のため、継いだ部分が耐えられないからです。ご了承ください。
- 見た目が写真と違う気がします
- 商品は一つずつ手作りのため、個体差があります。釉薬の塗り具合の加減で模様ができていることもありますが料理をするにあたっての支障はございません。
「目止め」のやり方
土鍋の小さな穴を、お米のでんぷん質でふさぐ方法です。おかゆのほか、雑炊やうどんを調理したり、片栗粉を溶かした水でも代用できます。
①洗ってよく乾かした土鍋に、水を8分目まで入れます。
②土鍋の中に大さじ3のお米(もしくは、ごはん、片栗粉など)を加えます。
③弱火から徐々に加熱しましょう。(中火まで)
焦げないように、時折木べらなどで混ぜながら、とろみがつくまで炊きます。
(急に強火で加熱すると割れの原因になるので、必ず弱火からはじめてください。
⓸沸騰後は弱火にして、おかゆがのり状になったら火を止めます。
⑤完全に冷めるまで、そのままにしておきます。(およそ1時間)
⓺冷めたら中身を取り出して、土鍋をきれいに洗い、しっかり乾かしてください。